INDEX
ボルドーワイン委員会(CIVB)は2024年4月17日、ボルドーワインの“今”を紹介するイベント「Undiscovered 2024」を開催した。
「Undiscovered 2024」は、ボルドーワインの新しい魅力を伝えるために、2024年からスタートした新プロモーション「Re BORDEAUX(リ・ボルドー)」の第1回目となるイベント。業界関係者向けのセミナーと試飲会により、コストパフォーマンスに優れたワインとの出会いの機会をつくることを目的とした。
当日は、東京都渋谷区の代官山 蔦屋書店を会場に、日本へはまだ輸入されていないボルドーワイン60種と、2024年の「Re BORDEAUX」を体現する厳選50種の試飲会に加え、マスターセミナーも開催。現地から6人の生産者も参加しての、盛りだくさんの内容となった。
マスターセミナーで講師を務めたのは、ソムリエでRe BORDEAUXプロフェッショナル・アンバサダーの石田博氏。ボルドーワインをテーマとして行われた3つの講義のうち、今回は「ボルドーの白ワインの現状と未来」について紹介する。

講師を務めた、石田博ソムリエ(日本ソムリエ協会副会長)
ボルドーの白ワインとは
フランス南西部に位置する、世界で最も有名なワインの産地、ボルドー。AOP(Appellation d’Origine Protégée、原産地保護呼称)のワインを生産する畑はフランス全土の4分の1を占め、AOPを取得した約5000の生産者が品質の高いワインをつくっている。
ボルドーといえば赤ワインのイメージが強く、生産量も圧倒的に赤が多い。その内訳は赤81%、白11%で、それ以外(ロゼ、クレマン、甘口)が計8%となっている。ただし、白ワインの比率は少ないとはいえ、無視できない魅力を持ち、生産者の数は2000にも及ぶ。
その特徴は、バリエーションの豊富さだ。主な白ぶどうの品種は3つあり、生産者が自由にブレンドの比率を決めることができる。爽やかな辛口から重厚でコクがある辛口、甘口の貴腐やスパークリングなどがあり、食前酒や食事と一緒に味わう食中酒、またデザートとしてなど、さまざまなシーンで楽しめる。
「同じワインでも、よく冷やせば食前酒に向き、温度を上げると食事に向く、というように、温度によって異なる表情を見せてくれます」と、石田氏は言う。
今回は、フレッシュなスタイルを一貫して守りながら、高品質な白ワインをつくり続けるボルドーについて、これまでの歩み、そして未来への取り組みについて見ていく。
白ワインづくりの歩み
実はボルドーという土地は、赤よりも白品種の栽培に向いているとされる。1957年より前、この地では実際に、白品種の方がより多く栽培されていた。しかし、白ワインへの評価は、ブルゴーニュと双璧をなすとされる赤ワインと比べて決して高くはなかった。赤ワインが注目されたことや、1956年の霜害などによって赤品種への切り替えが進んだことで、白品種の生産量は激減した。
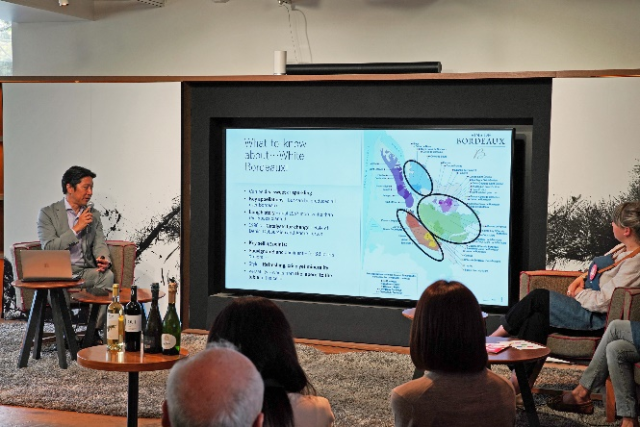
ところが、1990年代に白ぶどうの栽培技術や醸造技術が飛躍的に向上し、ブルゴーニュに引けを取らない品質を誇る白ワインがつくられるようになった。それに大きく貢献したといわれるのが、次の2人だ。
白ワインに革新的な変化をもたらした人物
1人は、ボルドー大学醸造学部の教授だったドゥニ・デュブルデュー氏。氏の提唱により、発酵前に果皮を果汁に浸して芳香成分を抽出する「スキンコンタクト」(後述)の技法や、ステンレスタンクではなく木樽で発酵させるといったアイディアが現場に取り入れられた。ボルドーの白ワインを洗練された辛口に改良する上で、主導的な役割を果たした人物だ。
もう1人がアンドレ・リュルトン氏で、スキンコンタクトと低温発酵の手法により、フレッシュでフルーティーな白ワインを確立した。かんきつ系のフルーツや黄色い花のフレーバーが特徴のこのスタイルは、1990年代に人気を博し、”フレッシュ&フルーティー”という言葉が白ワインの代名詞にもなったほどだ。
ボルドーの白ワインづくり
赤ワインだけではなく、白ワインの産地としても長い歴史を持つボルドー。ぶどうを育む土壌や3つの主要品種、ワインづくりを支える技術などにより、高品質なワインが生み出されている。
白ワインに使われる主な品種
ボルドーの白ワインに用いられるぶどうは、ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュスカデルの3品種が全体の97%を占める。これらを中心にブレンドした、さまざまなスタイルの白ワインがつくられている。
ソーヴィニヨン・ブラン(47%)
かんきつ類やハーブのような芳香成分を持つ、早熟型のぶどう。8月に収穫を始めるシャトーも少なくない。
セミヨン(45%)
穏やか、かつ奥行きのある香りを持つ、育てやすい品種。晩熟型で、熟成のポテンシャルが高い。
ミュスカデル(5%)
華やかな香りを持つ早熟型のぶどう。上記2品種と合わせて少量がブレンドされる。

他にも、ソーヴィニヨン・グリ、コロンバール、ユニ・ブランといった土着品種が補助的に栽培されており、全体の3%を占める。
さらに2021年には、温暖化対策として、湿度の高い気候に適したアルバリーニョと、カビに強いリリオリラが、ブレンド可能な新しい品種として認められた。
ソーヴィニヨン・ブランの芳香成分を育む土壌
ボルドーの土壌は、大きく分けて3つのタイプがある。ガロンヌ川とジロンド川の左岸に多いのが、保温効果の高い「砂利質」。一方、右岸に多いのが、比較的保温効果のある「石灰質」と、保水性に優れた「粘土質」だ。
ボルドー一帯は、湿潤な海洋性気候で気温の日較差(最高気温と最低気温の差)が小さく、土壌の保水性が高い。そのためぶどうの樹に対する水分ストレスが少なく、メイン品種であるソーヴィニヨン・ブランの芳香成分が安定して生成される。
もう1つ重要なのが土壌中の窒素含有量で、多すぎても少なすぎても芳香成分は少なくなる。ボルドーでは、そのバランスがうまくコントロールできているといえる。
芳香成分を抽出・保持するための技術
ボルドーでは、以下の技術によって白ぶどうのアロマを最大限に引き出し、ワインの特徴であるフレッシュさを守る努力が続けられている。
・スキンコンタクト
ソーヴィニヨン・ブランの果実を搾るだけでは、芳香成分を十分に得ることはできない。強くつぶしたり、果汁にアルコールが含まれていたりすると、好ましくないタンニンの成分が出てしまう。そこで、発酵させる前の果汁に果皮を漬け込むスキンコンタクトにより、芳香成分のみを抽出するようにしている。
・亜硫酸塩の適切な使用
酸化防止剤である亜硫酸塩を全く使用しないのではなく、適切に使用してフレッシュさを保っている。発酵中ではなく発酵後に入れることで、使用量を抑えつつ、クリーンなワインをつくることが可能となる。
・窒素ガスの活用
不活性ガスである窒素を、果汁やワインが通る場所とタンクに充填し、酸素に触れさせない状態でのワインづくりが行われている。
これらの他にも、醸造用の機械や酵母の選定、澱(おり)のコントロール、コルク栓をはじめとするクロージャーなど、より密閉性を高め、酸素を含まない嫌気的な状態を保つための工夫が数多く行われている。
未来へ向けて
ボルドーは、環境保全への取り組みが非常に早くから実施されてきたことでも知られる。その結果、現在はサステナブルなワインづくりを行う世界有数の産地となっている。
将来の気候変動を見据えて新品種を導入し、発酵から貯蔵に至るまで、さまざまな工夫を重ねるボルドー。有名シャトーだけではなく、小規模ながら個性的なワインづくりに取り組む、新進気鋭の醸造家や生産者も多い。

マスターセミナーには、シャトー・カルザンの生産者ネア・ベルグルンド氏(右から2人目)と、シャトー・カンカルノンのマチルド・アズレット氏(右端)も同席し、それぞれのワインづくりについて語った
常に時代をリードすべく新しいことに取り組むボルドーから、近い将来どんな革新的な技術やアイディアが生まれるか、注目していきたい。
次回の記事では、「Undiscovered 2024」で実施された石田博氏によるマスターセミナー「ボルドーの新世代の赤ワイン」について紹介する。







